包丁鋏など刃物研ぎに関するQ&A
刃物のこと、『研ぎ』に関することをよくある疑問や質問にQ&Aのかたちでお答えします。なおこの中にない疑問やご質問はメールにてお問合せください。質問箱にご返事を掲載します。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」おもわず「目からうろこ」ということもあるかもしれません。
実際、無知や間違い、勘違いというのは掃いて捨てるほどあることです。正しい知識を身に付けるのは、一生の得です。
庖丁編
研ぎについて、知っていて欲しいことがあります。それは、研ぎと修理があるということです。
新しい物でもありますが、何度か研いでくると、巾が狭くなったり、刃先のラインがおかしくなったり、また曲がりがきたり、丸刃になったりとプロポーションが変わってきます。
これを修正することが修理です。一般的には修理は研ぎの1.5~2倍程の料金がかかります。どこまでが研ぎでどこからが修理という境界はありません。包丁の構造や、形状によっても違いますし、研ぐ人や使う人によっても違います。
Q1、ステンレスでも研げますか?
A:セラミック(白い陶器製の物)以外は研げます。
Q2、古い物でも研げますか?
A:年数に関係なく研げます。ただし錆びがひどいとダメな場合もあります。錆びはひど なると鉄の内部にどんどん侵食して行きます。刃先の部分にこの錆びの侵食があると難しいのです。また、ステンレスでも錆びが出ます。
Q3、安い庖丁でもとげますか?
A:購入金額に関係なく研げます。ただし切味と切れ止みはその材質によって大きく変わります。
Q4、一度研ぐとどのくらいもちますか?
A:使い方、材質、使用頻度、まな板の種類によって大きく変わります。一般家庭なら2~3カ月が目安です。研いだときが一番よく切れ、使った分だけ切れなくなります。
Q5、研ぐより買い換えた方が安いのでは?
A:これは買う品物によります。1度研ぐのは500~600円ですが、600円で買える庖丁は全く良くないと言わざるをえません。しかも、新品の庖丁は多くが機会研ぎであるため、切味があまり良くありません。同じ庖丁でも、そのまま使うより研いで使った方がはるかに切れるのです。
Q6、研ぐと切れすぎて危ないのでは?
A:これは切れない庖丁に慣れているからです。庖丁は本来良く切れるという認識が緊張感を高め、指を切る事故を減らします。また切れる庖丁ほど力を入れなくて済みますので、誤って切った場合でも、軽いけがで済むのです。ちなみに、よく切れる刃物ほど手を切った時の後の痛みが少ないのです。
これは、切れない庖丁ほど刃先のオウトツが大きいので傷口を大きくしてしまうのです。これは、食材でも同じです。切れる庖丁ほど食材の組織をつぶさずに切れますので、新鮮でみずみずしいのです。
Q7、刃が欠けたものの研げますか?
A:だいたいの刃かけはなおります。庖丁の種類や場所によっても違いますので、ご持参いただきご相談ください。
Q8、柄の取替えはできますか?
A:和庖丁で木の柄がついているものは交換ができます。合板でビスで止めてある物や合成樹脂でできている柄はメーカーでなければ直らないです。
Q9、包丁は何回くらい研げますか?
A:何度でも研げます。ただ、研ぐ毎に少しずつ小さくなります。小さくなって使いにくくなったら寿命です。でも、ここまで使えは包丁も喜んでいます。
Q10、捨てる包丁はどうやって処分すればいいの?
A:新聞に包んで「燃やさないごみ」の日に出して下さい!金属ゴミとしてリサイクルします。また包丁の産地では11月8日を(いい刃の日)として刃物供養祭を開催しています。どなたでも、産地に送れば供養してもらえます。(送料は自己負担でお願いします)当社にお送りいただいても結構です。
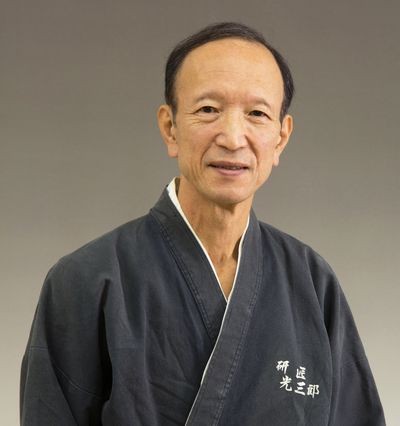
『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。
庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。
以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。
「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。
詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。
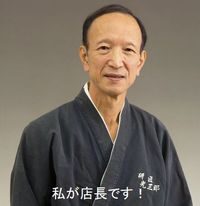
光三郎は感動の切れ味をお届けします。


