牛刀の構造は2種類ある
牛刀と言っても、長さが同じでも、形や幅はメーカーによっても、商品の種類によっても、まちまちです。刃の幅が広い物、狭いもの、刃先のカーブがきついもの、緩やかなもの、もちろん、柄の大きさや形も違います。
それから構造もちがいます。包丁を輪切りにした断面図を見ると、そのプロポーションはまちまちです。鋼材の厚みが違いますし、どの辺りから薄くなるかも違います。これによって、切れ味が変わります。
刃を薄くする程、切れ味は増すが、弱くなります。刃の先端まで厚くすると丈夫ですが、切れ味が落ちます。
それから、ほとんどのメーカーの包丁は左右対象になっていますが、そうでない物もあります。
牛刀の多くは構造は左右対象で、刃付けは7:3なってます。つまり、包丁を持った時の右側(表)が7、左側(裏)が3の割合で刃が付けてあります。
こうすることで、トマトや玉ねぎなどを薄くスライスする事ができますし、長年使って刃の幅が細くなっても、良い切れ味を保つ事ができます。
ここで刃付けが7:3ということですが、目指す刃角の7割の角度という意味です。私の場合、目指す刃角は23度ですので、約16度になります。
ほとんどのメーカーは左右対象に作ってありますが、一部メーカーや一部商品は和包丁の薄刃のように、裏がほぼ、0度(刃先でわずかに角度が付いてます。)で、表の方だけ角度が付いてます。正広の牛刀はすべてこのタイプです。その他、フィット工業の三元刃などがあります。
使いやすいは人それぞれなので、言及しませんが、理想を追求した一つの形です。しかしながら、このタイプか普及していないのは、従来品も研ぎ込めばほぼ満足できる切れ方になるからです。
長年研いで使うためには、刀身があまり薄くては、すぐにペラペラになります。最初は少し厚いくらいで、何度も研いで、刃先だけでなく、厚みも、徐々に薄くし、自分の理想形にしていくのです。
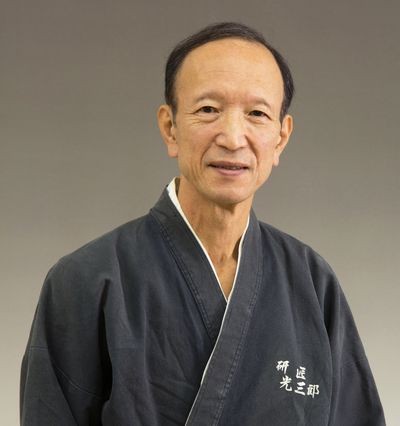
『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。
庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。
以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。
「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。
詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。
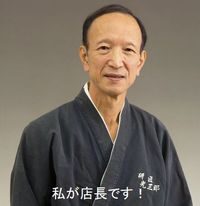
光三郎は感動の切れ味をお届けします。


