和包丁の構造上の種類(用途別の種類は別項で)
本焼き
打ち刃物です。包丁の峰の部分と刃先(切り刃)の部分の中ほどで接いである包丁です。写真で、上下という言いかたをすれば、峰部分の上の方が地金、刃先(切り刃)の部分が鋼でできています。切れ味は鋭く、切れる期間も霞合わせ(かすみあわせ)と比べると、3倍は長く切れます。鋼が非常に硬いため、研ぎは時間がかかり、難しいです。金額は霞合わせ(かすみあわせ)の3~5倍程度。鋼の種類(質)によって変わります。調理人が持つプロ用ともいえます。
霞合わせ(かすみあわせ)
打ち刃物です。一般的にはこの種類です。裏に鋼、表に地金が前後に合わせてあります。このため、刃先(切り刃)の部分に線が見えます。この線が鋼と地金の境目です。この線の模様は打ち方や鋼の種類によっても変わります。
霞張り合わせ(かすみはりあわせ)
裏に鋼、表に地金が前後に合わせてありますが、この場合は、2層になった、すでにできている鋼材を使います。通常は打ち刃物で刃ありません。そのため、霞合わせに比べると、切れが落ちます。特徴は厚みが均一であり、刃先(切り刃)の部分に線が直線です。柳刃に使うと都が多い。値段も少し安めです。もちろん材質によって、切れ味も、値段も大きく変わります。
全鋼
写真はステンレスですがすべて鋼でできています。厚さが均一で、刃先(切り刃)の部分に線はありません。全鋼とは言え、使う鋼は安価なものが多く、値段的にはもっとも安めです。これも、材質しだいです。
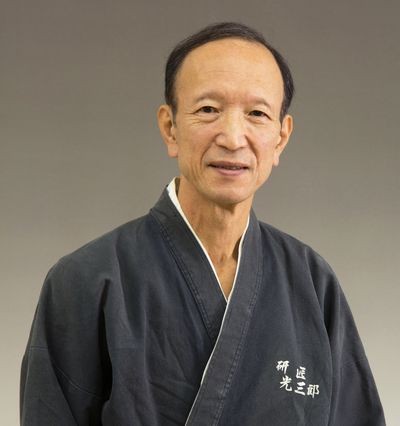
『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。
庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。
以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。
「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。
詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。
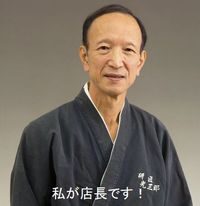
光三郎は感動の切れ味をお届けします。


