包丁の東型と西型は数種類の包丁に存在します。とはいえ、全部ではありません。あるのはサバキ、柳刃、うなぎ裂き、それから菜切り包丁です。
包丁は日本刀から発展しました。初期の包丁は日本刀のように束も長く、細長い刀のようなものでした。これが江戸時代になると徐々に幅が広くなり、今の菜切り包丁の原型のような形になりました。
江戸時代以前までは、刀鍛冶や鉄砲鍛冶が全国各地に発展しましたが、家康が天下を平定すると、需要が無くなった鍛冶屋が包丁や農具、工具作りなどに転職したであろうことが推測できます。
私の推測ですが、江戸時代になると、文化や情報の発信地は江戸となりましたが、それまで都があった京都や天下の台所と称されていた大阪などは面白くないのが当たり前。 そこで江戸に対抗するため独自の文化を作りあげたように思います。
菜切り包丁は『江戸型菜切り』とただの『菜切り』(西型菜切り)があります。
![39-2[1].jpg](/togisho/39-2%5B1%5D.jpg)
『江戸型菜切り』は切っ先とあごの丸みが大きく、柄も太く短い。
『菜切り』(西型菜切り)は切っ先の丸みは小さく、あごに丸みはなく、柄は細目です。
柳刃(正夫(しょうぶ)、刺身包丁)は当初江戸で『蛸引き包丁』として現われましたが、関西で現在の『柳刃』が現われました。
![14-3[1].jpg](/togisho/14-3%5B1%5D.jpg)
菜切りも柳刃も現在はともに西型が主流となっています。
また、うなぎ包丁は『うなぎ裂き』と呼ばれ『江戸裂き』、『京裂き』、『名古屋裂き』、『大阪裂き』と全く形の違う物を使っています。
![17-6[1].jpg](/togisho/17-6%5B1%5D.jpg)
![17-9[1].jpg](/togisho/17-9%5B1%5D.jpg)
当時、関西ではうなぎは腹から裂いていましたが、武士の多い江戸では腹切りは(切腹)につながると嫌われ、背から裂くようになったといわれています。
現在の和包丁は、江戸中期にはほ、ぼ完成されました。
洋包丁に関しては明治になって海外の食文化が入ってからになりますが、一般庶民に広まるのは、戦後になってからになります。
私は 29年生まれですが、子供のころ、母親は鋼の菜きり包丁を使っており、父親が砥石で研いでいたのを覚えています。
ステンレス包丁の本格的普及はそれからになります。 洋包丁で東型、西型があるのはサバキ包丁だけです。サバキ包丁は牛や豚、鶏などをサバキ、骨から肉をそぐのに便利です。東型が一般的ですが、サバク部位によっては西型がいいばあいもあります。
![32-7[1].jpg](/togisho/32-7%5B1%5D.jpg)
その他、地域地域で独特の形や構造の刃物も多く存在します。土佐の両刃出刃や石川鶴来のかわとり包丁、種子島の本種包丁など!
結局使いやすいのがよいと思います!!
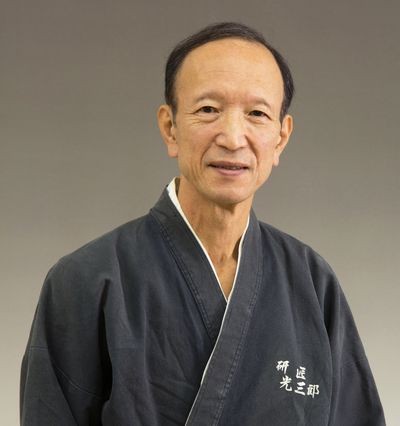
『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。
庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。
以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。
「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。
詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。
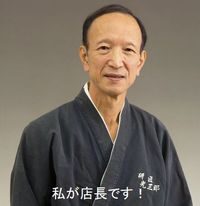
光三郎は感動の切れ味をお届けします。


