包丁の柄は清潔にしましょう。
包丁の柄を綺麗に管理している人は50人に1人で包丁の刀身(本体)を綺麗ににしている人は100人に1人くらいです。
みなさん、お料理には気を使い、努力や工夫を惜しまないようですが、事、包丁に関しては、全くと言っていい程ぞんざいです。
まず、包丁を洗わない方がおおいようです。水で流すだけでは洗うとは言えません。
最近でこそ、包丁の柄(ハンドル)にプラスチックなどの樹脂の柄がふえました。これは、抗菌性が高く、熱にも強く、扱いもらくです。これに対しで、合板の柄はこれに比べると、強度が落ちます。
落ちますと言っても、すぐではありません。手入れさえしていれば、問題はないくらいつよいのですが、食洗機にいれたり、常に水がついた状態であったりしますと徐々に劣化してきます。その上、食材の肉や魚を触った手で包丁を握る事が多く、これを洗わずに放置しておきますと、柄のつなぎ目や劣化したところに溜まってゆき、こびりついて取れなくなります。雑菌の温床どなり、とても清潔とは言えません。
包丁の柄の洗い方
柄を手前にくるように、包丁の刀身の峰を持つ。
写真を参考にして下さい。峰をしっかり固定して握る事てす。
一度握ったらこの手は持ちかえず手首を動かして、柄の場所
スポンジのかたいほうに少し、洗剤を付け、柄の周りをこすり洗いをする。(この時、刃先の下(アゴ)が当たらないようにする。
柄の圧縮合板はかなり強いもので、少々強くこすり洗いをしても大丈夫です。
包丁の付け根の部分はサビや汚れがつきやすいので、割ばしを平らに切って、汚れを落とすとよいでしょう。
みなさん、お料理には気を使い、努力や工夫を惜しまないようですが、事、包丁に関しては、全くと言っていい程ぞんざいです。
まず、包丁を洗わない方がおおいようです。水で流すだけでは洗うとは言えません。
最近でこそ、包丁の柄(ハンドル)にプラスチックなどの樹脂の柄がふえました。これは、抗菌性が高く、熱にも強く、扱いもらくです。これに対しで、合板の柄はこれに比べると、強度が落ちます。
落ちますと言っても、すぐではありません。手入れさえしていれば、問題はないくらいつよいのですが、食洗機にいれたり、常に水がついた状態であったりしますと徐々に劣化してきます。その上、食材の肉や魚を触った手で包丁を握る事が多く、これを洗わずに放置しておきますと、柄のつなぎ目や劣化したところに溜まってゆき、こびりついて取れなくなります。雑菌の温床どなり、とても清潔とは言えません。
包丁の柄の洗い方
柄を手前にくるように、包丁の刀身の峰を持つ。
写真を参考にして下さい。峰をしっかり固定して握る事てす。
一度握ったらこの手は持ちかえず手首を動かして、柄の場所
スポンジのかたいほうに少し、洗剤を付け、柄の周りをこすり洗いをする。(この時、刃先の下(アゴ)が当たらないようにする。
柄の圧縮合板はかなり強いもので、少々強くこすり洗いをしても大丈夫です。
包丁の付け根の部分はサビや汚れがつきやすいので、割ばしを平らに切って、汚れを落とすとよいでしょう。
 |
 |
 |
 |
 |
|
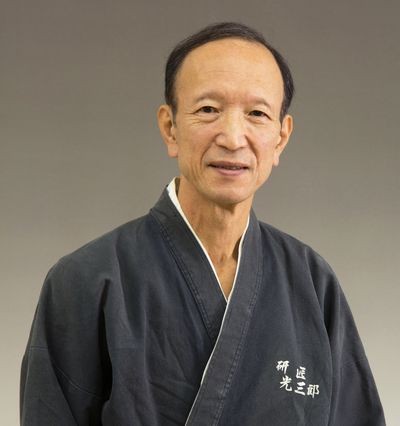
『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、庖丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。
庖丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。
以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さんやお母さんが研いでいました。そういった人が高齢化し、年々その数が減少し、その反面お困りの方が増えています。『研匠』光三郎はそんな人の悩みを解消し、毎日のお料理が少しでも楽に、楽しくなればと考えています。
「庖丁とはこんなに切れる物なの?」という驚きと感動を日本中の人に伝えたいと考えています。
詳しくは以下の会社紹介をご覧ください。
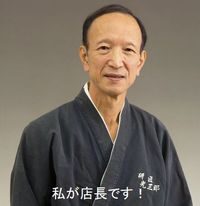
会社紹介-Company- | 研匠光三郎
経営理念 『研匠』光三郎は、研ぎを通じて、包丁(刃物)の本当の切味を提供し、楽しく、気持ちよいお料理環境を創造する会社です。 包丁等の刃物は、現在研ぐ所がないため、多くが使い捨てになっています。 以前はどこの家庭にも「砥石」があり、お父さん
光三郎は感動の切れ味をお届けします。


